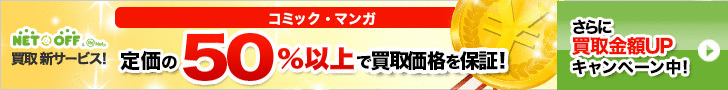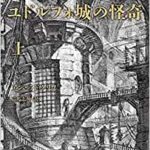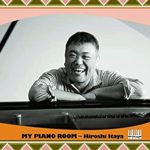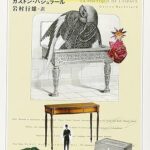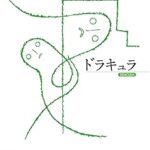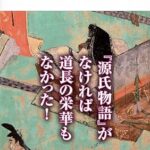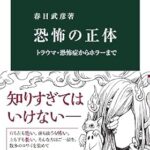- 現代日本最高峰の散文の更新
- 現代日本最高峰の、老いの繰り言
- 現在と過去との交歓
- おススメ度:特になし(もはや、お薦めする/しない、という次元の問題ではない)
古井由吉の新刊。これが小説なのかどうか分からない。散文なのは間違いないが、小説として読むと、何が何だか分からなくなるかもしれない。むしろ古典を読むような感じで、古人の随想を読むような感じで、本書に著されているものを、過去の遺文として掻き分けるようにして探ると、かえってすんなり頭に入るかもしれない、というそんな断章の数々。ふと道端で出会った老境に入った人物の、何を話しているのかよく分からないけれど、それでも何かすごいことを語っているような、そういう心構えで文章のほつれを噛み砕くと、まるで古老の語りのような、いにしえより連綿と口伝えで渡されてきた、未来の予言としてその隔たりが測れるかもしれない。
自らの現在の状況と、若いころやもっと幼いころのこととがない交ぜになった語り。あるいは、手術後の入院時におけるような、まるでせん妄状態に見る「幻覚」を宿しているような。だとすると、ある意味幻想小説なのかもしれない。後藤明生式にいうと、現実そのものがすでに幻想的な光景であるような、そんなかんじ。それはもしかしたら、時間と空間との距離の取り方そのものの、暦を重ねるごとにおける変容のせいなのかもしれない。
「時間にせよ空間にせよすべての差異が、隔たったものがたやすく融合する」現在において、自身の身の内にあらゆる時間空間が流れ込み、収拾のつかないままに見る現れとしての意識。とはいえ、そうした意識を書きとめる著者は、「すべておのれが空間と時間の中心からはずれたところから来る」意識にも沈んで、時空間の遠近は行ったり来たりする。老境に入った者の、その時間の感覚は、ひとしなみに押しひろげられた紙のように伸ばされて、その上を自在に行き来できるという錯覚を生じた自らの視点の移動を伴うことで過去は一様さを失い、それらすべては複雑にからみあって現在に流れ込むのではないか。つまり、過去の数十年の出来事が、それぞれの時間性の隔たりを失って、空間的に同じ距離に布置されているように見えてくることがあるのかもしれない。
何らかの見当識を失ったと思しき著者の語りは、「勘のもどるのを待つ」ように、狂いと正常の挟間に押し込まれながら、じっと通常の意識を、病状の安定を待つように待つ。そこで待っているのは、もちろん病気からの癒え、あるいは症状の安定でありながら、狂いからの抜け出しでもありつつ、また、ある意味動物的感覚でもって、執筆における萌しの到来を待っているようにも思える。そこで行われている<待つ>とはもはや、何かを待つための<待つ>ではなくて、<待つ>ことそのものが予兆として持つような、さきがけとして感じられる、そういう<待つ>。それが文章として書きとめられるときにようやく了解されるような<待つ>は、通常の意味においては意味をなさないけれど、そんなものがあったかのようにここでは感じられる。それは、過去と現在との往還が自在に行われるせいでもある。
著者が待っているのは、窮極的には、<死>のことであるかもしれない、と読む限りではそうとれないことはない。それは未来のことであるのだけれど、「老いの苦しみの後の、わずかな安堵」を含むであろう<死>をひそかに想う、その態度がしめすものは、世間での名もない大勢の<死>を反省的におのれへ照らしながら、いつかの自身の「行方知れず」の道行きを思っていることなのかもしれない。そこではもう、<待つ>ことすら「行方知れず」になって、何も思うことのない未明の白い闇へと溶け込んでいく時に上げる、ひそやかな哄笑だけになった、著者自身の名残が響いているだけかもしれない。
私は、本書を、2月に入ってから、一日につき、一章ずつ読んでいた。この2月は、先年に比べてまったく寒い日がなくて、去年は氷点下8度ほど記録したが、今年は氷点下3度が幾日かあったきりで、例年ならば凍えるような寒気の風に震えながら歩いているところが、今年は中旬過ぎからすでに花粉が舞いだし、そうかと思うと最高気温も2月のそれではなく、歩くたびに額に汗のにじむのをあやしんでいた。普段ならば春の来るのを待っているところが、今年は待つまでもなく、待つことを思うでもなく、待っていなかった暖かい風が強く吹き抜けていた。
かすかに裸木の枝の梢のほうが揺れるだけであったものの、その暖かい風にからまれてさわさわと片方から片方へと行き交う枝の群れは、そこにもうすぐ咲くであろう桜の花を待たされているのが思われ、その他にも、コナラやハンノキやらの枝が、痩せ枯れた人たちの腕の諸手を挙げて踊るのにも思えて、狂院をめぐりて暗き盆踊、という西東三鬼の句が頭に浮かんだ。作者の自解によると、敗戦翌年には京都の精神病院まわりの、暗い辻々では人々が盆踊のように夜更けまで踊っていたものらしい。病院の内外では誰もかれもが狂ったように踊りあっていたという、そういう時勢を句の暗きに重ね合わせて、この句をよむたびに自身の内から湧きあがってくる暗い情念の凝ることを思う人がいたという。
裸の枝は死んでいるような気配を漂わせつつも、そこからは未だ膨らまないつぼみの予兆は知れるわけで、同様に、未見のその盆踊の光景はまぶたの裏にうかべられて、私は、すでに桜の花を何らかの真実在としてそこに見ている。桜の開花を待つとはすでにして冬の間から思われているわけで、もしかするとそこにこそ春の桜(ソメイヨシノ・ヤマザクラ)を待つことの想いがこめられているような気がする。期して待つからこそ、待つことにも飽きはじめてしまうわけで、そうしてようやく満開の時の、遙かな時の隔たりが一瞬に埋められることの驚きがそこには隠されている。
今年の冬は、まったく寒くなかったので、道端の池や水たまりがかたく氷つくことはあまりなかった。いつもなら、霜の白く泡立ったのが冬の花びらのようにも見られることになる。山家集の、山おろしの木のもと埋む花の雪は岩井に浮くも氷とぞ見る、といううたは最新の校註によると、岩井に浮かぶ花を氷に見立てた珍しい着想のものらしい。どう珍しいのかは分らないが、これは実際に見た光景ではないのではないか。むしろ、氷の薄く張った水たまりの、小さくひびの入ったその様を花に見立てたと読んでもいいのではないか。私としては勝手にそう読んでいる。そこから春の花の光景を思うこともできるのではないか。
同じく山家集にある、雪と見えて風に桜の乱るれば花の笠着る春の夜の月、というものはふつうに読むととくにこれといって面白みもなさそうだが、これも実際に見た光景ではないと読めば何か別の読み方ができそうではある。まず月というのは西行にとって重要な信仰の状態を表すアイテムなわけで、それに暈がかかったように見えてしまう花の散らばりは、未だ夜にあるという彼自身の心的状態を表しているのではないだろうか。単なる光景ではないということなのだが、これが当たっているかどうかはともかく、夜に見る花というのは現代においては重要な心的契機になるのではないだろうか。つまり、月の光の下で見る桜ではなくて、道端の街灯に照らされた桜の木と花に、何かしらのあこがれが生まれてもいいのではないかということである。私はいつも、街灯のあかりに照らされている、ただ独り立っている桜の木と花に、言い知れぬ想いを抱くのであります。
さて本書を読むのに一番良い状態というのがあります。それは、大病や怪我からの回復の目途がたった、その萌しがみえはじめて、ようやく人心地ついた時の、何とも言えない人間の世界にようやくたどり着いた時のような、病みつくした底をようやく通り越した後のような、そういう回復の道筋がついたときに読むと、実は身にしみます。ちょっとした風邪からの回復の時を思い浮かべてみると、いいかもしれません。まあ、どうでもいいことですけど。
(成城比丘太郎)