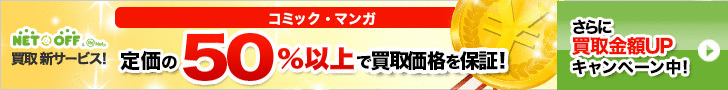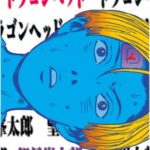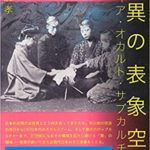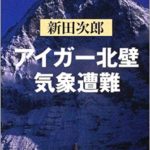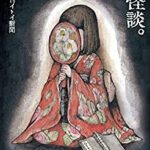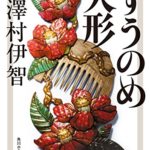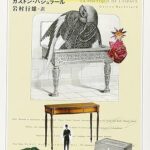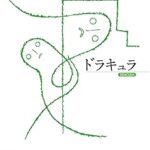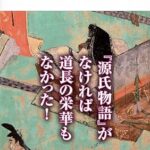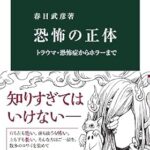- 「ファースト・コンタクトもの」
- 惑星エデンに不時着した6人の探索行
- SFというよりファンタジーに近い部分もある
- おススメ度:★★★☆☆
レムの『エデン(EDEN)』は、《未知のものとの出会い》として書かれた三部作のひとつです。本書の後に、『ソラリス』(Ama)・『砂漠の惑星』(Ama)
と続きますが、おもしろさというか読みごたえとしては後者の二作の方が上だと思います。でも、「未知のもの」と接触しそれらとどうコンタクトしたらよいか、またはそれらとの実際の(翻訳を通した)対話という面で見ると、「他者」となんとか意思疎通しようとする乗組員の努力があって、それがよいところ。とはいえ、『ソラリス』以降の作品と比べると、(哲学的な読み方としては)かなり平板にならざるをえないという印象なのは否めません。しかし、物語として単純だからこそ、地球外生命体には地球人にも理解可能なもの(翻訳可能な)ものがあるのかともいえる余地がうまれるのかもしれませんが。本書には、なにものかとのコンタクトという点において、地球上の生物に対するコンタクトへの類似が見られるかもしれません。だからこそ、接触不可能という断念に対しては、なんらかの猶予がうまれるのかもしれません。
本作品は、言ってしまえば「惑星間ロビンソンクルーソー」です。惑星エデンに不時着した宇宙船から這い出した6人の男どもが、それぞれのキャラ(というか立場)を代表するかのような役どころでもって、この惑星探索にあたろうとします。彼らがこの惑星で出会うのは、地球上のもの(に少し似ているものの、そう)ではない奇妙な生物たちです。もちろん、それらの形状などは地球のものと似ているものはあるのですが、生態とかそれに類するものが違うようです。一行は惑星探索において、それら不思議な生物や用途不明な建造物や飛行物体などをひとつずつ確かめながら、それらがどういったものなのかを議論していきます。このあたりはまあ、SFものというよりも探検ものといった感じです。
「ここ[=惑星エデン]で起こっていることはみんな、どれをとってみても、部分的には地球で知られているいろんな事象に似ている点に注意して欲しい。しかしどの場合にもそれは部分的でしかない。どうしてもいくつかの空欄が残ってしまうんだ」(『エデン』p147)
その「空欄」とは、彼ら(というか乗組員の一人であるドクター)がおぼえた、この惑星における不思議なモノどもと、地球の生態(あるいは生体・政体)との間にある理解しがたいともいえる(し、翻訳して知ったともいえる)非連続的な両者のありようの違いに存在する空隙でしょうか。もっというと、エデンの住人との意思疎通において、何かそれを妨げるものがありそうでなさそうなのがあって、個人的にはおもしろい。
彼らが対話しようと試みるのが、「複体生物」というエデンの住人です。この「複体生物」には脳がなく、体には二つの機能を有しています。この住人から聞きとった(翻訳した)エデンの内実は、それなりに興味深いものがあるものの、私としてはとくに深いものがあるともいえません。むしろ、この複体生物とのあれやこれやのやり取りの方に、なぜかおかしさをおぼえてしまいます。
【まとめと、余談】
本作品は、一応SFだと思うのですが、もしこの舞台を地球外の惑星ではなくて、地球上のどこかにある異世界(?)のような場所に設定し、そこへの探検ファンタジーにしたとしても、とくに違和感なく読めるような気もします。まあ、地球外の惑星だからこそのおもしろさはあるのでしょうが。
あと、『ソラリス』との違いでいうと、本作品をもし映画化したらどうなるかと頭の中で映像化してみたら、なんとなく安っぽいホラー(?)にしかならなかった。本作を、例えば『遊星からの物体Xファーストコンタクト』と比べてみたらどうでしょう。『遊星からの~』は、地球上に飛来していた地球外生命体とのファーストコンタクトを描いたものでした。この映画に出てくるエイリアンとは全くコンタクトがとれないので、パニックホラームービーのような感じです。さらにそこへ加えて、エイリアンが人間になりすますことができるので、サスペンスの要素もあります。この映画と比べると、『エデン』では乗組員がエデンの住人に細胞レベルで乗っ取られるなんてこともなく、乗組員同士が疑心暗鬼に陥るなんてこともないので、なんとなく呑気な惑星探検といったかんじです。
(成城比丘太郎)