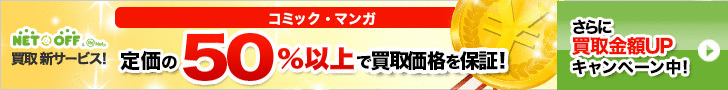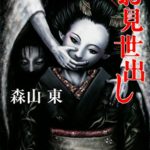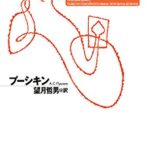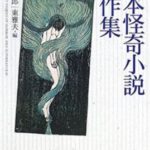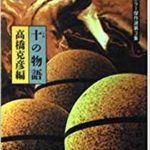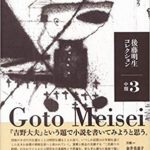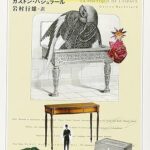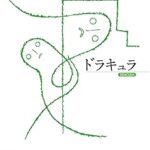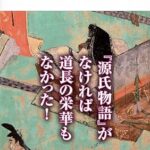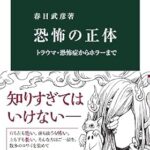- ソローキンの傑作
- 前半は、ロシア文学の系譜に連なるロマン
- 後半は、すべてが解体されていく
- おススメ度:★★★★☆
【はじめに】
ソローキンの『ロマン(POMAH)』は、傑作(怪作・快作)ですので、このような紹介文など読まずに、何も知らずに読んでいただきたい。なので、ここで終わります、と書くとアホでしかないので、一応何か書きたいと思います。もしネタバレなしで読みたい人は、ここでページを閉じてください。
【わけのわからん紹介】
本作の主人公はロマン。去年(2018年)の日本では、コペル君を主人公とする本(漫画)がベストセラーになりましたが、もちろん本書はそれと何も関係がない。コペル君の名前の由来は、コペルニクスからきたのでしょうが、それはいいとして、本書は、天地がひっくりかえったかのような衝撃が痙攣的笑いとともに読者に押し寄せる(はず)。後半の「リズミカルな反復」による強烈な聖なる感動が前半部分に胚胎しているように感じられて何度でも読みたい気分(になるかも)。
舞台は19世紀末のロシア(と思われる)。ロマンは、都会から田舎のクルトイ・ヤール村に戻ってきたのです。彼は、都会での弁護士業を辞めて、この村で新たに画家になることをめざすのです。彼の性情は、「感じやすく大胆で情動の激しいタイプの人間」というものですが、後半における彼にはそのような情熱が消されて単なる殺戮マシーンへの傾斜が見られ、また次第にその作業自体がまるでゲームのような単なるルーティンワークのパッチワークになるのですが、その話はまた後で。
ロマンは村に戻ってきてから様々な歓待を受けます。叔父叔母からのテンションの高い歓迎を受け、その他知り合いの教師や医者やからも同じように久しぶりの帰郷をよろこばれます。すがすがしい春の自然と、村の人との再会が待っていたのです。そんな知り合いとのやり取りの中で、「死への意志」や「創造する人間に必要なのは自由だけだ」というような何らかの思想が、ロマンのなかに孕まれていって、それらは後の展開に通じるようなかんじがあります。基本的には、「ロシアの笑いの力と純粋さ」の中で、彼の新たな人生は幕を開けようとするのです。新生です。まるで新しい年を迎えたかのような気分になれるかもしれません。復活祭前のうきうきとした雰囲気もかんじられます。
ロマンはある日のキノコ採集において、オオカミと激闘をくりひろげ、大けがを負います。普通ならこういった事件は何らかの生に対する啓示ともなって、文学作品としても重要な転機にもなるようなことなのでしょう。これが何を意味するのかは本書ではどうでもよくなります。そんな村での新しい生活で、彼を待ち受けていたのは、タチヤーナという女性との出会いでした。やがて彼女に惹かれたロマンは、タチヤーナの父と、なぜか彼女をめぐりロシアンルーレットをすることになるのです。なぜかは知りません。この「死」を賭けた勝負にロマンはすげぇ興奮するのです。この展開は、ドストエフスキーさんの死刑執行の前に恩赦が下ったという、あの何ともいえない恍惚とした経験に通じるような気もしないでもない。
そんなこんながあって、ロマンはある事件を通して、ようやくタチヤーナと婚約をし、すぐさま婚礼の儀式を上げるのです。二人は、集まった知り合いや村人の前で、幸福の絶頂にしてはいささかやりすぎな儀式を執り行います(これがロシア的?)。この世にあることの奇跡と幸福と情熱的なやりとりと、列席者のカーニヴァル的なドンチャン騒ぎ。そして式が終わった夜、ロマンとタチヤーナの二人は、二人への贈り物である斧と鈴になんらかの天啓を受けたのかどうかわからないが、この二つのモノを持って、次々に村人を襲いまくるのです。まずは、ロマンの叔父叔母を含む親しい人々への襲撃。ここの描写はまだリアリズム風を装っているものの、眠っている村人を次々と斧で屠っていくありさまになると、無双モードのように淡々と描かれます。「~の家に入る」、「~が寝ている」、「~の頭(や肩や背中など)に斧をくらわせる」などといったシークエンスの繰り返し。まだ息があるものにもう一度斧をくらわせ、立ち向かってくるものに斧をくらわせ、起きているものには挨拶をして斧をくらわせ、その間、タチヤーナは持っている鈴を儀式のように鳴らし、延々と殺戮は続くのです。その後、二人は教会に向かい、タチヤーナは鈴を鳴らし、ロマンはより一層、一切の価値判断を排除されたかのような純粋なテクストのみのリフレインにとりつかれたように読める行動の実践者になります。それからは、精緻なテクストで作り上げられた巨大なオブジェを見るという経験によって、笑いの痙攣を伴う陶酔にひたれることでしょう。なんとなく、ポオのメエルシュトロノームに呑みこまれたかのよう。最後に待ち受ける、「ロマンは~した」という行為(の表記)の連続において、ロマンはおろか、書き手も読み手もテクストすべてが、この小説(ロマン)そのものとともに解体されて、読後は妙にすがすがしい法悦をおぼえることでしょう。
(成城比丘太郎)