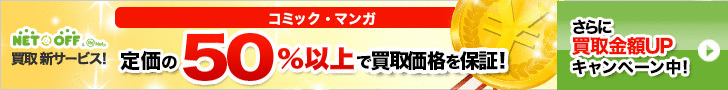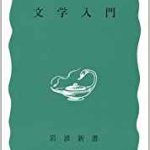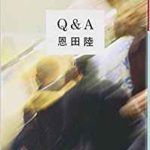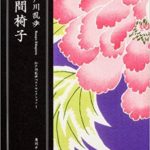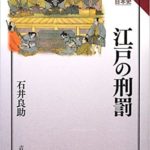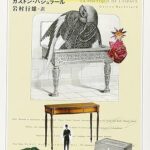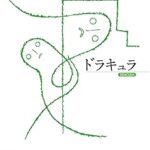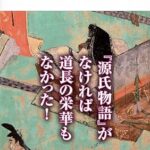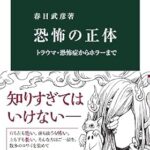- 超自然現象を、結構冷静な目線で。
- オモシロ怖い怪談を含むホラー短編集。
- 何かを感じるということについて。
- おススメ度:★★★★☆
E・F・ベンスンは、「イギリス怪奇小説の名匠」ということで、丁度100年前に作品を多数発表した人物。『怪奇礼賛』というアンソロジー本によると、「合計百冊以上の本を出したベンスン三兄弟の一人」で、また(おそらく)訳者の中野善夫はそこで「そろそろ日本でもベンスン短編集をもう一度出してもいい頃だと思うのだが、どうだろう」と奈辺によびかけたのやら分かりませんが、こうして20年経ってようやく新たな短編集が出版されたようです。今月(2018年2月)にもまた新たな短編集『見えるもの見えざるもの(Amazon)』が出版されたので、これを契機に、本棚に大事に(?)しまってあった本書を手に取りました。このブログに記事を書きはじめてから約一年、あまり積極的に読まなかったホラーを、ここ最近意識的に読むようになったおかげ(?)。しかし、日本のホラーにはあまり手が出ず、なぜかホラー(ファンタジー含む)系小説というと海外ものを今まで通りメインに読んでばかりなのですが(しかしスティーブン・キングはもうここ20年も読んでなく、なぜか読む気も起らないので、これはきうら氏に任せてます)。
まあ私のことはいいとして、このベンスンについて乱歩が何と言っているのか急に気になったので、「怪談入門」という評論をパラパラ読んだら、ベンスンは「優れた怪談を幾つか殘してゐる」として、「Negotium-Perambulans」というナメクジ怪談が最も面白かったという簡単な紹介。この短編は読んだことがない。調べたらちくま文庫に収められているようなので、図書館で借りて読んでみよう(ちなみに本書には、大量の芋虫が出てくる『芋虫』という作品があります)。乱歩はその評論で、(広義の)探偵小説とよんでいるのは探偵小説と怪談とを包含するカテゴリーだ、みたいなことを書いてました。いつの時代の探偵小説についても私は門外漢ですが、はるほど、この『塔の中の部屋』も探偵は出てきませんが、心霊現象などの不可思議を探ろうとするところはあるので、その謎解きを楽しむのはそうなのでしょうか。とはいえ、何か込み入ったトリックがあって、その謎を解くというより、先の見える展開、つまり結末がある程度見通せて、その作中の謎を覆う靄みたいなのを追い払うように読んで結末のオチにたどり着く感じなので、謎解きとは厳密には違うのでしょうが。
ベンスンの生きた時代はおそらく心霊主義が盛んの頃のことなので、交霊会が出てきます。『広間のあいつ』という短編では、「巨大なナメクジの影のよう」なものが壁を這いより、最終的にそれが実体化して二人の人物をおそろしい死へと導きます。この一編は本書の最後にもってきていますが、これは、「尋常ならざる現象」を追究した結果どうなるかということを示しているのか。
本書では、(当時の)科学から超自然現象を捉えようとしたところがあって興味深い。『扉の外』では、ある女性の幽霊現象の科学的な(?)説明がなされるのですが、彼女が言うには、人の頭〔脳〕から発せられる波が物理的なものとして屋敷などに痕跡を残し、心霊現象をうみだすという知性的な幽霊分析(当時としては納得的だったのか)。また、『夜の恐怖』では、感情が何らかの物質として伝わり、それに感染した者が恐怖に怯えるというようなさまがうかがえる。
表題作の『塔の中の部屋』は、夢で見たことが現実に起こるということについての話。そこでは「私」が15年間も断続的に見続けた悪夢のことが語られます。その内容とは、「私」がある館に招待され、いつもとある部屋に招きいれられるというものでした。しばらく経って、現実の世界で「私」が友人に招待されたのもその館だったのです。そして……。演出がコテコテのホラー映画みたいですが、なかなかのおもしろさ。
私(=ブログ筆者のこと)もたまに同じ怖い夢を見ることがあります。その内容とは、繁華街を歩いていた私が、気付くと道をそれていて、それまでの喧騒が消え去った通路に入りこんでいて、街灯はひとつも点いておらず、暗がりに家のシルエットだけが浮かんで、もちろん人の気配はなく、しかしなぜか何かいるという気配だけはあり、私はおそるおそる足を踏み入れていくのです。その時の心理状態(?)は夢なのに怖さとワクワク感が合わさって自分ではかなり楽しく、何か出てこないかなー、でも出てこないでほしいなー、と背反する気持ちでいるのです。まあ何も起こらず通り過ぎてしまい、夢は別の場面に移行するか、目が覚めるかするのですが。たまに、見上げた時に満天の星がうるさいくらいに瞬いていて、それに圧倒されることがあるのですが、それが何を示しているのかちょっと調べたら、なんか吉兆らしいんですが、とくにそれからなにか良いことが起こったということはありませんでした。
本書には幽霊そのものを扱った普通の短編もあります。『チャールズ・リンクスワークの懺悔』は、死刑になった男が、この世へ干渉して、医師と電話をしてあることをやり遂げようとする話。なんか残留思念のような魂が懺悔する話。『土煙』では、人の霊も出てきますが、車のものも出てきます。文章にもスピード感があるように思えて、当時のモータリゼーションへの感慨を見るよう。その他、『レンガ窯のある屋敷』とか、『もう片方のベッド』とかありますが、『かくて恐怖は歩廊を去りぬ』は、幽霊現象が日常茶飯事に起こるある一族の怪異譚で、一族の幽霊への親しみと恐怖と哀れみを感じさせる一品。
それ以外にも色々あって面白かった。『遠くへ行き過ぎた男』は、「開放と休止と受容の姿勢」で自然を受け止めよう、一体化しようとする男の話。ある感得、完全な知識への感得への奮えが、文章自体の自然への敬愛に乗りうつったかのようですが、最後に、この男には神話的存在のきつい一撃が待っていたのです。
『ガヴォンの夜』や『ノウサギ狩り』は、「土着の魔術」(「解説」)に関する話で、『ノウサギ狩り』には、スコットランドのある地域に住む黒いウサギがもつ伝承のことが語られていて興味深い。ここには、単なる迷信とは言えない迫真さがある。
『霊柩馬車』に出てくる登場人物のある言葉がイイ。「もちろん、私は恐怖を感じるのが好きなのさ」「ぞっとして、ぞっとしたあげくに、もっとぞっとしたいんだ。恐怖というのは、何より人の心を奪う芳醇な感情だ。恐怖を覚えたとき、人はほかのすべてを忘れてしまう」という単純ながら真をついた発言。本書はこういったことを感じさせてくれる。古くさい恐怖だと感じるかもしれませんが、日本のホラーがこういったものを取り込んでいったからなのか。まあともかく、私は十分楽しめた。
(成城比丘太郎)