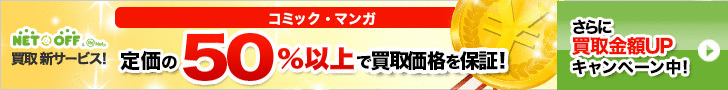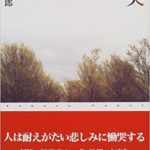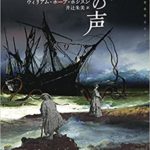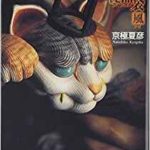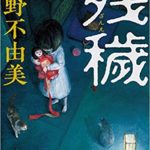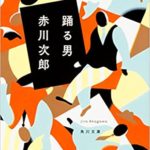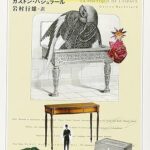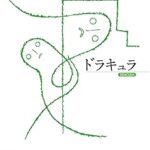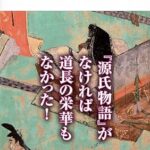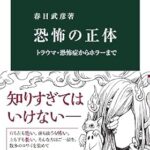- 読書メモ(034)
- 古代から現代までの「幽霊」表象を追う
- 様々な学術的見地から多角的に「幽霊」を捉える
- おススメ度:★★★☆☆
【はじめに】
新元号が、「令和」に決まりました。はじめ、「れいわ」と聞いて、発表された文字を見てから5日くらいは、どこかしっくりこないものがありましたが、これを書いている現在10日を過ぎると、見慣れてきたというか、おそらくあと数カ月もしたらまったく違和感なく受け入れているでしょうね。というか、個人的に、学術的な立場からこの「令和」に否定的な意見が出てくるかなとほんのすこしだけ期待したのですが、どうもエモーショナルな否定意見しか出てこなかったようです(私の見た範囲では)。
ほんで、私は「令和」に関して詳しく言うことはないですが(万葉集を引っ張り出してみたものの、元号に使用された当該個所は読んだ覚えがなかった)、ひとつだけ思ったことがあります。「れいわ」と聞いた時に、すぐに、頭の中で《霊話》という熟語?に変換しました。幽霊の話、と書いたものを縮めて、霊話です。おそらく日本国中で、「令和」を《霊話》とダブらせた人は、500人くらいはいると思いますが、公式にそれを申し述べた人はいなかったようです(たぶん)。
【本書について】
上記のようなわけで、本書を読んだ、というわけではないです。たまたま、3月31日から本書をちらちら読みだしただけです(たまたまの、たまとは、霊魂の魂に通じはしないでしょうが)。それもあって、4月の新元号発表時において、「令和」を《霊話》に読み替えただけというのもあるかと思います。これから先、誰も「令和」を幽霊の話とかぶらせて語る人は現れないでしょうが、本書を読むと、幽霊というものの表象が人間にとって非常にユニークで、文化史的に興味深いことがわかります。
本書には、編者を含む13人(!)の著者が、幽霊に関する何らかの分野に拠って、執筆した論考を収めています。カテゴリーとしては、「幽霊の存在論」、「幽霊の表現論」、「幽霊の空間論」に分かれています。幽霊の存在論とは、古代から近世にかけての幽霊というものがどのようなものとして存在するか、ということを書いたものです。「霊魂や幽霊、死霊とは本来いかなるもので、どのように表象されたのかを検討した」ものです。幽霊の表現論とは、文学作品や芸術作品や映像作品などに現れる幽霊の表現方法について。幽霊の空間論とは、「幽霊や神霊がどのような場所に出没するか」ということについて。
ここで重要なのは、古代(8世紀)から文献上に現れる「幽霊」の文字とそれが意味するものは、現代のそれとはかけ離れているかもしれないということでしょう。「古代の「幽霊」は、近世になると、モノノケや化物、怨霊と明確には区別されなくなっていく」ということを考えると、「令和」の出典先となった万葉集に描かれている当時の人々の精神構造は、現代人とは全く異なる部分があるやもしれぬということです。とくに「幽霊」みたいなものについてはそうでしょう。字面からは判断できない、古代人と現代人との違いに敏感にならなければ、新元号のもつ意味を取り違えることになるとは思えませんが、万葉集に載せられた古代人たちの生活における思想を、現代にも同様なものとして通じるというノンキな読みには注意しなければいけないと改めて思いました。なぜかというと、私個人が、昔そのような無邪気な読み方をしていたからです。今でも変わらない部分はありますけど。
さて、本書で興味深いのは、幽霊とゾンビとの存在論的位相を扱った論考でしょう。これは現在進行形でその表象を変えてきているので、考察しがいがありそうな分野でしょう。それから「デジタル時代の幽霊表象」について。ここでは、監視カメラやYouTube上の幽霊動画やらが、「体験不可能」という意味で、不可知論的な「死」の映像化が観る人を不安に陥れるとしています。とはいえ、そもそも、「フェイク」や「やらせ」でしかない幽霊動画であったとしても、それは逆に言うと本物の幽霊とは何なのかという語りきれない問題が浮かび上がってくるようにも思えますが。さらに本書では、様々な形で、幽霊表象は「不可視なものの可視化」という立場に立つのですが、この「死の可視化」とは、しょせん「死」の代替物としての表象でしかないので、幽霊表象自体がもつ生々しい直感という言説化できない部分は見えない。というか、見えないからこそ、幽霊動画は怖くないのでしょう。でも、現代における幽霊像を考える上では、おもしろそうではあります。
それから、心霊写真のことも面白いです。現在はデジタル画像ばかりになりましたが、そのデータベースから幽霊らしきデータを取り出してくるというのがおもしろい。映像データ(YouTubeなど)から「無意識」的なものとしての「幽霊」を事後的に発掘するというのは、幽霊表象の新たなメディアにおける受容なのではないかと思います。ほんで、ホラー映画の幽霊表象とメディアの物質性に関するものも面白い。その物質性は、たとえば『リング』の「貞子」においては、まずビデオテープからはじまって、のちに別の幽霊がデジタルネットワークを通して人を呪いに感染させ、現代では、様々な幽霊(貞子)表象がネット上(SNS上)において、「ゴースト」化して流通しているところまでに至っています。
ところで、『リング』の映画よりも、映画の前に放送されたドラマの『リング』(高橋克典・主演)の方がはるかに怖かったんですが、あまり話題に上がらないなぁ。まあ、昔の話ですけども。
【まとめ】
本書は、おおまかに日本の幽霊に関して、様々な分野から理解できるものになっています。とくに、現代の幽霊についてはなかなかおもしろかったですが、ホラー漫画やホラー小説についてはほとんど述べられていなかったのが少し残念。
(成城比丘太郎)