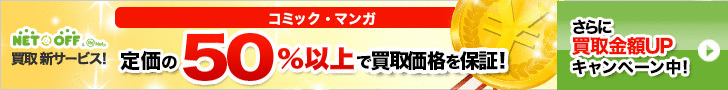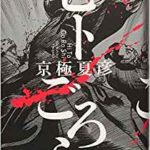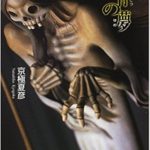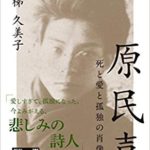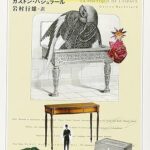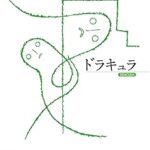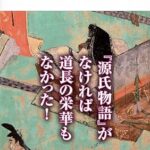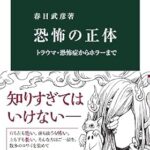- 読んで心地よい不朽の名文
- 素敵な世捨人ライフ
- 無常感というよりむしろエネルギッシュ
- おススメ度:★★★★☆
【ご挨拶】
今年最後の更新がなぜか古典。まあ、世知辛い世の中、一年の締めにはふさわしいとも思っている。まとめ記事はお正月に公開予定なのでお楽しみに。今年も一年間ありがとうございました。来年もできる限りホラーな小説ライフを送りたいと思っています。では良いお年を!
【本文】
20代の頃に読んでそのまま本棚にあったのを、特に理由なく今回再読してみた。例の冒頭のフレーズが秀逸すぎて、頭に残っていたのだが、その内容の印象は大分違うものだった。
知らない人はまずいないはずなのだが、本題の前に簡単に紹介を。1212年(鎌倉時代)に成立したと言われる鴨長明の随筆。随筆という言葉を調べると「心に浮かんだ事、見聞きした事などを筆にまかせて書いた文章」とある。まあ思いついたことを書き留めた文章だと思えば間違いないだろう。和漢混淆文で最初期に書かれた優れた文学ともある。内容は世の中と我が身の儚さを語りつつ、隠遁して得た発見が瑞々しい書かれている。タイトルは随筆が書かれた終の住処の広さ方丈(約3m四方)から。
まずは冒頭を書きたい。原本は損なわれていて写本を底本にしているため、内容に諸説あるが、今回はネットでの可読性を考慮して青空文庫から文章を借りてきた。訳によって仮名遣いや送りが違うのでご注意を(底本:「國文大觀 日記草子部」明文社 )。
行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとゞまることなし。世の中にある人とすみかと、またかくの如し。
何度繰り返して読んでも心地よい日本語である。私は古典文学者では無いので、細かい用語や差異にこだわらず、一つの物語として読んでみたい。一応、ホラー的観点からも読むという無謀なこともしてみる。
まず、中盤までは世の中の儚さ怖さを結構リアルに、敢えて言えば恐ろしく描いている。原文を読んでる最中は、文章が端正なので分からないがよくよく意味を調べてみると、残酷な描写が繰り出されている。例えば、飢饉で死骸が町に溢れ死臭がたまらないとか、地震で子供が下敷きになって目玉が3センチ飛び出したとか、かなり怖い。それぞれ引用するとこんな感じ。
ついひぢのつら、路頭に飢ゑ死ぬるたぐひは數もしらず。取り捨つるわざもなければ、くさき香世界にみちみちて、かはり行くかたちありさま、目もあてられぬこと多かり。
その中に、あるものゝふのひとり子の、六つ七つばかりに侍りしが、ついぢのおほひの下に小家をつくり、はかなげなるあとなしごとをして遊び侍りしが、俄にくづれうめられて、あとかたなくひらにうちひさがれて、二つの目など一寸ばかりうち出されたるを、父母かゝへて、聲もをしまずかなしみあひて侍りしこそあはれにかなしく見はべりしか。
こういう描写は極端だが、貴族が落ちぶれて物乞いになる様、出世競争に破れて崩れゆく都に住む様子、竜巻で家財が吹き飛んだ事件など、世に起こり得る悲惨をつらつらと書いている。これが世の中にある人と栖と、またかくの如しということだろう。
ただ、私が方丈記を好きな理由に、これだけの無常を語りつつ、決して絶望感がないことである。むしろ、柔らかい調子で「世の中こんなもんでしょう」と諭されている気がする。いや、諭すどころか、独り言のようなもので、教条的に人生を語っているのではない。
後半は、そんな鴨長明が、山に狭い家を建て、一人暮らす様子が語られる。「落ちぶれたものだなぁ」という感慨は多少あるものの、世間の些事に惑わされない今の生活がいかに素晴らしいかを語っている。
元はけっこう大きな神社の次男で、歌の世界でも名を馳せた鴨長明は、たまに町に出ると、自らの貧しい身なりを恥じるとは書いてあるが、あくまで人の目が気になる場所限定で、庵に帰ってくると落ち着くのである。麓の少年と遊ぶなど、実に微笑ましくていいシーンだ。
かしこに小童あり、時々來りてあひとぶらふ。もしつれづれなる時は、これを友としてあそびありく。かれは十六歳、われは六十、その齡ことの外なれど、心を慰むることはこれおなじ。あるはつばなをぬき、いはなしをとる(りイ)。
前半の嵐のような終末世界の描写と見事に対比されていて、ここに「俺も世を捨てて、こんな風に生きたい」と思わせる魅力がある。さらに、こんな風に「独り」の素晴らしさが述べられている。
二つの用をなす。手のやつこ、足ののり物、よくわが心にかなへり。心また身のくるしみを知れゝば、くるしむ時はやすめつ、まめなる時はつかふ。つかふとてもたびたび過さず、ものうしとても心をうごかすことなし。
ものうしとても心をうごかすことなしか……そして、独りでいることの最大のメリットはこう語られている。
一期のたのしみは、うたゝねの枕の上にきはまり、生涯の望は、をりをりの美景にのこれり。
まあ好きな時に働いて、疲れたら休み、良い景色を見て、眠い時にはうたた寝する……確かに理想郷だ。ただ、これを教義にするのではなく、
すべてかやうのこと、樂しく富める人に對していふにはあらず、たゞわが身一つにとりて、昔と今とをたくらぶるばかりなり。
と、あくまで自分自身の感想であると断っている。ただ、途中、友達に対して「だいたい利益のある人に寄ってくるものだ」と嘆息しているのは、どうだろう。ここには少し違和感が無いでもない。「友達って大事だよね!」などと明るく断言する気は早々ないが、無常な世界を生きる同志として、友は貴重だと思っている。
ラストは悟ったような、若干の迷いのようなことが語られていて、なかなか味わい深い。総じて川の流れのように語られる言葉は、繰り返し読んでも飽きることなく、また心地よい。虚無感よりも人間的な浮き沈みを、愛情を持って語っている気がする。
しかし、自分には世捨て人の最後の敵である孤独はどうするのかという疑問がまだある。それもしょせん「心をうごかすことなし」なのだろうか。その辺は深く理解できていないが、他人を頼らないから、他人を苦しめないという思想は「他人を苦しめてナンボ」という現代へのカウンターともいえる。
しかし、こんな生き方は可能だろうか? やれ100億稼いだの、誰それが不倫したの、どこかの誰かが悪口を言っただの、頼みもしないのに、喧しく伝え聞く日々。しかしそれは、この現代日本の暮らしと不可分で、もはや人と交信を絶って生きるなど、ほとんどの人間には不可能だ。清濁併せ呑んで、せいぜい苦海を泳ぎ切るしかないだろう。
そういう意味では、飢饉や火事で人が大勢死ぬ時代と、過労やいじめで多数が死ぬ現代と、相通じるものが多分にある。と言うかどちらも生きることの本質ではないか。だからこそ、この随筆は伝え読まれてきたのだろう。
ちなみに、本文は非常に短い。30分もあれば読めるだろう。本書にはその後、現代語訳と参考文献、鴨長明の年譜と解説なども収録されている。現代語訳はやや味気ないが、一部の難解な本文の理解に役立つ。本文にも丁寧な脚注があるので、大抵の人はこれで理解できるだろう。なので、これから読む人には青空文庫よりも、書籍版を勧めたい。
最後に共同運営者の成城氏に方丈記の話をしたら、ぜひ、ちくま学芸文庫版を推挙したいとのことなので、ここにリンクを貼っておく。彼は私より遥かに文学に通暁しているので、こちらを読まれるのがオススメだ。プレビューしてみたが、最初に解説から始まっているのでこちらの方が読みやすそうだった。
【ちくま学芸文庫版「方丈記(浅見和彦 校訂・訳)」】
(きうら)