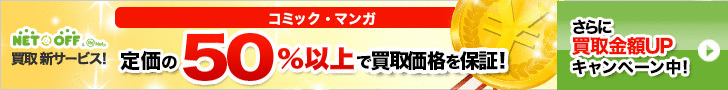- 去年末から今月にかけて読んだ本
- ホラー、歴史、文学、エッセイ
- 怪奇ものはおもろいです
- オモシロ度:それぞれ
【怪奇幻想もの】
・ルゴーネス『アラバスターの壺/女王の瞳』(大西亮〔訳〕、光文社古典新訳文庫)
アルゼンチンの作家ルゴーネス(1874-1938)の短編集。18編の短編が収められている。ルゴーネスは、ボルヘスやコルタサルの源流に位置する幻想文学作家。本書は、オカルティズムやオリエンタリズムに由来する「面妖・怪奇」な奇想あふれる作品集。とくにルゴーネスの人を食ったような機知と博識ぶりに驚かされる。ちょっと古い感じの側面もありますが、これこそが19世紀20世紀前半の怪奇文学だと思う。では以下にちょっとだけ、作品紹介を。
死んだヒキガエルが復讐する「ヒキガエル」。
生命を吹き込まれた骸骨と生きた人間との照応を描いた「カバラの実践」や、インドで憑依された猿の影に取りつかれた人物のことを書いた「不可解な現象」には明らかなオカルティズムが見える。
表題作の「アラバスターの壺」と「女王の瞳」は、古代エジプト王朝のファラオの呪いと、現代に生きるある女性とがつながりをもって、それが恐怖の源泉となることを示す作品。
「考える主体としてのわたし」を失くしたが死者へと変貌と遂げる「死んだ男」。鏡と人間の想念との共鳴を描いた「黒い鏡」。円の完全性に取りつかれた狂人の行末を描いた「円の発見」。毒のあるスミレをつくろうとする庭師のことを描いた「ウィオラ・アケロンティア」。音の振動をエネルギーに変えようとする人物のことを書いた「オメガ波」。これらは、著者の博識や奇想がいかされたなかなか味わい深い作品たち。
この短編集の特徴は、ファムファタールめいた人物が出てくるところと、語りの構造に多層的な面があって、そこらへんがおもしろかった。
【歴史もの】
・和田裕弘『織田信忠』(中公新書)
戦国時代において、有名大名の嫡男とされる人物には、将来を嘱望されながら若死(討死・横死)したものがたくさんいた。個人的に気になるのは、尼子政久(経久の子)、織田信忠、松平(徳川)信康、長宗我部信親など。とくに信忠と信親は生きていたらどうなっていただろうかと、たまに考える。信忠以下の三名は信長から名前をもらった。その信長の後継者であった信忠は父親ともども本能寺の変でその未来を閉ざされた。本書では、その信忠の業績や人物像などを、歴史史料から丹念に追っていく。これを読む限りでは、戦に関しては武田攻めや信貴山城にこもる松永久秀攻めなど、かなりの武功をあげていて信長の重臣などからかなり期待されていたようである(武田滅亡に関しては信忠が大きな役割をもった)。ただし、なぜか人物の逸話は少ないようで、実際どんな人物であったのかは、はっきりと見えてこない。そのわけは、信長という存在が大きすぎたからかもしれない。というか、これからの人物だったのだろう。
もし本能寺の変で信長だけが死に、信忠が逃げ延びて(チャンスはあったという)、近江なり岐阜なりで態勢をととのえて光秀と対峙できていれば、その後の歴史はどうなっていたかは分らない(しかし、信長ほどの能力をもっていたかはわからない)。そういう意味で、かなり社会的影響力はあった人物と推察される。本書は、信忠研究の一助になりそうな本だった。
ところで著者は、家康の伊賀越えに関して疑義を呈している。「それほどの危険があったのだろうか」と書いている。それはそうかもしれないとは思う。もしその時に家康さんたち一行の状況判断が楽観的なものなら(それはあり得ないとは思うが)、甲賀から伊賀へ抜けた方が伊勢に出るルートとしては楽だったろう。土地に明るい人もいただろうし。大和から伊勢へ直接抜けたかもしれないと書くが、では、どのルートを通ったのだろうか。現在でも、大和から直接伊勢に出るには、けっこうな山越えのルートになる。家康さんたちに危機感がそれほどなかったのなら(何度も言うが、危機感はあったであろう)、甲賀に出た方がいいと愚考するんだが。もちろん、道案内がいれば大和から伊勢の北畠館に抜けたほうが簡単なルートだとは思うが。著者はなぜか、この箇所だけ歯切れが悪い書き方に終始している。個人的には、それよりも、穴山梅雪がなぜ一行から離れたかのほうに興味がある。
では、明智光秀が信長を襲ったのはなぜか?これについては、要因を一つに絞るのはまだ困難だと思われる。あくまで個人的見解を書くと、それまでに信長さんは何人にも背かれてるから、今回の謀反が決定的だったということつまり信長と信忠の脇が甘すぎただけか。もしこれが戦国シミュレーションゲームで光秀でプレイしていたなら、このままだと天下は統一されてしまい、単に領国経営で終わる人生になってしまう。下手したら佐久間信盛のように追放されるかもしれない。それならばと、ここで逆転の一手を打って独立大名として名乗りを上げようと思うだろう。もしゲームならそうしている。
【文学(日本)】
村田沙耶香『生命式』(河出書房新社)は、《食す》ということへのこだわりが見える作品集。ちょっと内容の出来にばらつきがある。死者の肉を調理してそれを食ったふたりがまぐわい、死者の生命を得ることで新たな生命を引き継ごうという「生命式」。人体の部分を再利用する社会を描いた「素敵な素材」。食文化の違いからそれぞれの認識が改まる文化相対主義的な場面を描いた「素晴らしい食卓」など、いずれも何らかの違和を生じさせることによって、読者のいる位置を揺さぶろうとする。しかし、それほどの衝撃はない。何かが足りないと思うんだが、それが何かは分からない。設定に寄りかかりすぎなのか、そこから何の思想もうかがえないからか。
今村夏子『あひる』(書肆侃侃房・角川文庫)も同じく、食べることがよく出てくる作品集。こちらは、普通に読んでいると、子供が出てくるかわいらしい作品と思ってしまいそうだが、しかしそんなにほんわかしたものではない。本作品は子どもでも読める内容なのだけども、ちょっと注意して読むとイヤなところがにじみ出てくる。これが村田沙耶香にはないものか。表題作の「あひる」に特徴的だけど、真夜中に飯を食いにくるこどもとか、あひるのことを全部知っていた子どもとか、よく考えると(考えなくても)、変なところをへんなふうには書いてなくてもそれを変なものとして捉えさせてくれるところにほんのりとした怖さがある。
本書に、とある現代詩人について以下のような評言があった。
「震災後の特需景気に乗って、簡易ブログで安易なたれながしの詩を乱発して増長し、名士となった若手詩人」(p39)
このような「ブログ」で、自分勝手な感想を「たれながし」ている私からしたら、「名士」でもないのにちょっと耳が痛いといいたくなるとまではいわないけど、まあ個人ブログはそんなもんだろう。でも問題はそこではない。それにしても、「詩人」を修飾する言葉としてはなかなかのものである。この「若手詩人」の名前は書かれていないけど、おそらく私が購読している某新聞で詩の寸評をしている人のことだろう。もしそうだとするならば、私としてはその詩人には今まで何の感慨も抱いたことがない。震災後にメディアに出まくって詩を疲労していたときにはそれを読んでもなんとも思わなかったし、新聞に月1回連載しているものを読んでも、おそろしいほどの凡庸さだなとしか思わない。それと同時に、「これ、どのくらいの人がきちんと読んでるんやろ」としか思わない。つまり、このような詩人が「名士」として持ち上げられるほどに(?)、現在の詩壇は衰えているのだろうか、ほどにしか思わない。今でも、ネット上には個人の詩があふれていると思うけど(昔、私も書いていた)、そんなところから「名士」として持ち上げられてしまったというのは、もし本人に「素朴」で「単純」という認識があるならばこれほど不幸なことはない。たぶんないと思うけど。小説というのは素人にもある程度出来不出来はわかるけど、詩というのはよくわからないことも多い。もし「ものの見方が単純」な詩が隆盛をきわめるのならば、これから日本の「現代詩作家」のありようは変わってくるだろうなぁ。詩人として生きていくなら、まずは名前を売るところからはじめるか、もしくはヒットソング(歌手)にでも歌詞を提供していくしかしかないんだろうか。
【文学(海外)】
・サミュエル・ベケット『名づけられないもの』(宇野邦一〔訳〕、河出書房新社)
1969年度ノーベル文学賞の候補に井上靖があがっていたという報道が、先日あった。井上靖は生前、賞を欲しがっていたということを聞いたことがあるが、もしあと5年生きていたら安部公房か彼のどちらかが受賞していたのだろうか。
その1969年に受賞したのがベケット。そのベケットの小説三部作(『モロイ』・『マロウンは死ぬ』とこれ)が去年新訳で出版された。あくまで私が見た範囲だと、どこでも話題になっていなかった。私も今月ようやく三作目を読み終えたけども、これといって書くほどの感想がない。というよりも、これは感想など書けないなと思いながら読んでいた。もし感想を言うとしたら、これを読んだ人たちで何か読んだ時の印象を語るしかないなと思った。
おもしろくないわけではなかった。とくに『名づけられないもの』は、書くという行為のギリギリのところで書いているなというその臨場感は伝わってきた。シオランはベケットと仲がよかったそうではあるが、なるほど分かるような気がした。ちなみにシオランはブランショを批判していたようだけども、私はブランショの小説は数ページで挫折した。それを考えると、ベケットにはまだ何かを書くという明確なヴィジョンみたいなものがありそれは見えた気がする。
ベケット三部作については、また数年後に最初から読み返してみよう、と思わせるものはあるので、何かしら引っかかったものはあった。ここでは感想を書かないので、以前私がある人物から聞いたベケットにまつわる話を脚色して、創作風に書いてみます。
そのことを私に話してくれた彼は、その当時都会の方に出かけていて、住んでいる郊外へ向かっていつものように、夕方には鉄道の人になっていた。その時は夕方に発車する急行に乗っていて、ターミナル駅からしずかにぬけだした車窓から見える空は、真っ青だった昼のものから薄く白い色が刷毛ではかれたように幕がかぶされて、それは傾き始めた陽光によるものだと思わせて、彼はまた一日の終わりを移動する空間に揺られることになれてしまったことを思っていた。
その時も定刻通りに発車した列車から見える、駅のホーム向こうに見えるマンションの通路には灯りが白くともっていて、暗くなりはじめるであろう建物の外に広がる空との奇妙なとりあわせに、季節が夏に向かわせることを思わせたという。
彼はいつものように見ていたそのマンションの通路を、背筋を伸ばして歩いている女性の姿を認めたという。水色系統の上着だけが見えて髪の長さは肩のあたりまでだった。ふだんなら気にもとめないのだが、その時には妙に気になったのだという。動いていく風景からちょっとだけ見えたその姿に。
やがて車窓からはそのマンションも見えなくなって、いくつもの見慣れた都会のくらいビルだけが流れていき、続いて線路の上を覆うようなかたちではしる高速道路がその陰を車内に落としていった。車内は、見たことのない人たちが、見たことのあるような格好で車内に腰掛けているのが、とたんに視界に入ってきたように意識された。
しばらくして列車は次の駅に着いた。乗り継ぎ駅になっているその駅からは乗客は増えて、彼の前のシート席は満員になっていた。その時彼は、彼の前に座ったある女性にある注意をとめたという。肩までの髪に、すらりとした長身、真ん中から分けられた前髪からはするどい鼻梁がのぞいて、少しとがり気味の顎に向けて口元はまとめられていた。彼女のことに気付いたときの彼女は、うつむき加減でいたけれども、彼は一瞬にして、その人が先ほど見たはずのマンションの通路を歩く女性に酷似していることにも気付いたという。
他人の空似というわけではなかった。なぜなら、先ほど見かけたその女性の横顔をしっかりと確認できたわけではないから。その女性の顔などは全く見ていなかった。
――つまりだね、その僕が見たマンションのひとと、乗客の姿がまったくかぶっていたんだよ。
――それはつまり、そのふたりが同じだったと言いたいのか?
――いやそれはありえないね。
――だったら、君の思いこみか、それとも、そのふたりが姉妹か何かだという可能性もあるね。
――そう、そうなんだよ。その姉妹説が一番ありそうだけど、それじゃあ他人説よりもつまらないだろう。
――いや、つまらないかどうかは知らないが、たとえばそのふたりが姉妹だとして、彼女たちは駅前のビルで買い物をした後、姉の方は住んでいるマンションに戻り、妹の方は実家に戻ったんじゃないかな。
――まあそれでもいいんだけど、おもしろいのが、その乗客の方が、本を取り出して読んでたんだけど。
――へぇ、何の本?
――それがさぁ、ベケットだったんだ。
――ていうと、あのベケットか、ゴドーの。
――そうそうそれ。
――それが何か気になったのか?
それから彼は、彼女がベケットを読みはじめたその情景を語った。彼によると、おそらく読んでいたのはそのゴドーだったのではないかとのことだった。彼が言うには、彼女の姉がおそらく劇団員かタレントか何かで、その彼女が出るはずのベケットの劇を見に行くために、その予習としてベケットを読んでいたのではないかということだった。乗客の彼女は、なぜか一度もこちらの方に目をあげずに、ずっと下を向いて本を読んでいて、彼によると読むというよりも頭の中に文字を埋め込むのではないかと思えるほどの熱中ぶりで、かと思うと内容など入っていないかと思わせるような目の泳ぎ方で、それは不思議な読書の仕方で、それを読む主体である彼女の方が逆に、その本自体に読まされているのではないか、つまりその本が本体で、彼女自身は、その本自体のオマケだったのではないかという印象を受けたという。そして彼の話はそこからあらぬ方へ飛んで、乗客の方の彼女は実は、マンションの方から身を分けられたものではないか、というもので、彼が言うには、今ベケットを読んでいるのは彼の目の前にいる彼女そのものではなくて、あのマンションの一室にいる彼女の方ではないかということだった。
私はそんなことはあり得ないと言ったが、彼の異様で迫真的な話し方と、その光景を見ていない私としては、彼が受けた印象そのものは信じてもいいと思った。おそらくその時の彼は疲れていたのだろうと、私は彼のことをそっとしておこうと思っただけだった。
私は、あなた疲れているのよ、という言葉をのみこんで、彼に、それでその乗客の方とは話とかしてみたかと訊いた。彼は、そうする雰囲気ではなかった、と言い、彼女が彼の降りる駅よりもはるか手前の駅で降りていくのを見送ることしかできなかったという。
彼の話しぶりには、もちろん嘘をついている感じはなかったし、そもそもそういう何かしらの感応というか、何かと何かを関連付けて何かを考えることはあると思ったのだ。つまりは、彼はその彼女とやらに惹かれたのかもしれないと、そう思っただけだった。そして私は、言ってはいけなかったかもしれない言葉を彼に発してしまった。
――じゃあさあ、その彼女とやらに会いに、マンションに行けばいいんじゃね?
私の発言を聞いて、彼はその時までの愁眉を払って、瞳を冬の雲間から覗かせる青空のように輝かせて、何かをつかんだように、じゃあ今度そのマンションとやらに行ってみる、と言った。その瞬間、私は駄目なことを言ったのではないかと後悔しかけたが、彼の瞳の輝き自体にはそれほどの悪意のようなものは感じられなかったので、一応は安心したのだった。
それから半年以上は彼に会わなかった。私も気にかけていたものの、彼が無茶なことはしないだろうと思っていた。実際に、彼の周囲からは彼に対しての悪評は聞こえてこなかった。
次に彼に会ったのは、春を迎えて明るさの混じったカフェでだった。彼も私もあの時の話題には触れずに近況を報告した後、やはりあの事が気になっていた私は、冗談っぽく彼にその後のことを訊いてみた。ところがなんと、彼はその時私に話したことを全くおぼえていなかった。マンションの女性のことも、ベケットを読む女性のことも、何もかもおぼえておらず、そんなことを私に話したことすらも初耳だと言った。彼のその瞳に嘘の感じは全くなかった。私はかなり熱心に、その時彼が話したことをおぼえている限りで彼に語り、彼がどれだけその女性に執心した様子を見せていたか、そしていずれその女性に会いに行くことを語っていたかを、彼に伝えた。だが、何もかも彼はおぼえていなかった。ベケットという単語にも全く反応しなかった。そのマンションすらおぼえておらず、駅前に確かそんなマンションがあるな、という具合の反応だった。やがて憑かれたように語っていた私が語り疲れると、そんなことを熱心に語っていた私のことを彼が心配しはじめ、挙句の果てには、彼は私に向かって、じゃあ君がその女性に会いに行けばいいじゃないか、と言った。
(成城比丘太郎)