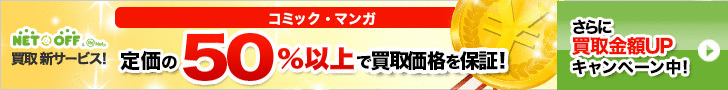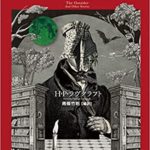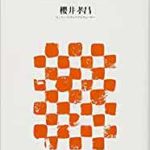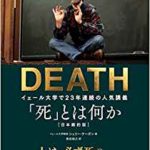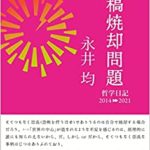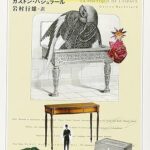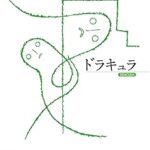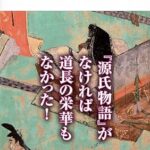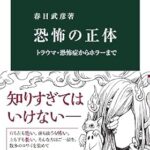- コラム(015)
- 夏休みに読みたい作品
- 夏の100冊読み比べ
- おススメ度:特になし
【はじめに】
このブログの主要目的はとくにありません。基本的には本などを読み、映画やアニメなどを観て、その感想を書くだけのものです。たまに、他の人(ブログ読者)への紹介として記事を書くこともありますけども、だいたい自分勝手なことをダラダラと書いてます。それがブログの一つの利点(?)でもあるので、これからも雑談を続けていこうと思っています。てなわけで、これから定期的に雑談というか、とっちらかした話題を書いていくと思います。まあ、はっきりいうと雑録的・日記的なものです。
【夏休みに読みたい短編への補足】
去年(2018年)の同じ時期に、「夏休みにおすすめする短編」のことを書きました。今回、その補足をしようと思ったのですが、なんだか面倒になったので、適当に書きたいと思います。
夏休みに読書をする人(生徒さん)はあまりいないと思います。とくに小説を読む人は少ないと思います。そんな人向けに、青空文庫で簡単に読める作品を少しだけ紹介します。前回のおすすめ記事にも書きましたが、葉山嘉樹の「セメント樽の中の手紙」 (角川文庫)は本当に簡単に読めるので、読書気分を盛り上げていきたいという人には、そのとっかかりには最適です。
それから、一番おすすめなのが、芥川龍之介の「尾生の信」(青空文庫)でしょう。私は全く青空文庫を利用しないのですが、この作品は、おそらく青空文庫のなかでは、一番といってもいいくらいすぐに読めるものと思います。読書なんかメンドイと思う人でも、本当にさっと読めます。一種の幻想小説ですので、ファンタジー好きにもおすすめです。これ読むだけで、芥川の作品いろいろ読んだで、と自慢することができます。
それから青空文庫で読める芥川でいうと、芥川龍之介の「あばばばば」(青空文庫)も簡単に読めてなかなか含蓄のある作品です。去年(2018年)に放送されたアニメ『こみっくがーるず』では、主人公に「あばばば・・・」という口癖を付与させていて、それがひとつの持ち芸になっていました。もちろん『こみっくがーるず』と芥川の「あばばばば」とは何の関係もありません。私はこのアニメのことを友人に話したときに、芥川の「あばばばば」のことを教えられて家にある芥川全集で読みました。というか、この作品読んだことがあるかタイトルを見たことがあるはずなのに覚えてなかった。今読んでも私も感じたことのある、なかなか興味深い人生の機微に満ちあふれた好編です。
【夏に読みたいホラー】
夏に読むものといえば、やはりホラーではないでしょうか。このブログでも色々取り上げているので、ホラーのタグをクリックしてもらえば、なんやかんやと記事が出てきます。そして、そこに付け加える一冊が発売されました。先月、新潮文庫から南條竹則編訳で、『インスマスの影』というタイトルのラヴクラフト新訳が出ました。これのいいところは、「750円(税別)」という比較的お手頃価格でいろんなクトゥルー神話作品を味わえるところでしょう。ほんで、まだ私はこれを読んでませんが、パラパラめくってみたところ、翻訳は読みやすそうです。本書には、「恩田陸氏震撼」という惹句が載せられています。なるほどそうなのか、といったかんじです。
【あまりおすすめしない作品(反語)】
さて、最近、『危険なヴィジョン・1巻』(ハーラン・エリスン編、ハヤカワ文庫SF)を読みました。その中に収録されていたフィリップ・ホセ・ファーマーの短編「紫綬褒金の騎手たち、または大いなる強制飼養」(山形浩生・訳)が、なかなかぶっとんでいました。ちょっとここではあまり書けない、というか書きたくない単語のオンパレードでしたし、内容的にも理解できない部分もあったのですが、生ぬるい作品に飽きた人にはおすすめしたいです(もし面白くなかったとしたら勘弁して下さい)。
【夏の100冊を読む】
毎年恒例の「新潮文庫の100冊」に加え、角川文庫のもの・集英社文庫の「ナツイチ」のラインナップを読みました。ざっと読み比べたところ、この三者に共通する作品は、『人間失格』 (新潮文庫)と『星の王子さま』 (新潮文庫)
のみのもよう。夏目漱石は、集英社だけが『坊っちゃん』 (集英社文庫)
で、あとは『こころ』です。ほんま、『人間失格』は強いなぁといったかんじ。『星の王子さま』は訳者がそれぞれ違うので、これは別物と考えてよいかもしれない。そう考えると、なんで『人間失格』ばかりなのだろうか。新潮くらい別の本にしたらいいのに。
さて、今、手元に、過去の「夏の100冊」があります。1995年の「新潮文庫の100冊」と、1996年集英社文庫の「ナツイチ」で、新潮のものは永瀬正敏が表紙で、「ナツイチ」は広末涼子が表紙になっている。
新潮のやつの、1995年と2019年のものを比べてみると、まず、海外作家が減っている。適当に数えると、今年のものは17人で、1995年のものは31人。20年以上経って、人数が約半減している。その分、現在のものは現役日本人作家やノンフィクション作品が増えている。日本人作家も、過去の名作に関しては大幅に減っている。
何より驚いたのが、1995年の「100冊」フェアでは、クイズに答えると、パソコンや自転車が当たる。「ナツイチ」(1996)では、ブックカバーや広末涼子のテレホンカードがそれぞれ2000名に当たる。この時の広末涼子はCMに出始めて、ロンバケでは、ツンツンしたあとからのデレ演技を見せて人気が上がり始めていた、そういう時期だった。
先に、過去の名作が減ったと書いたけれど、25年経ってもしぶとく残っているものもある。芥川龍之介(蜘蛛の糸・杜子春)、安部公房(砂の女)、遠藤周作(沈黙)、井伏鱒二(黒い雨)、梶井基次郎(檸檬)などなど。海外作家で残っているのも、カフカやカミュやドストエフスキーやモンゴメリなどの有名作品のみ。ここで面白いのは、95年では谷崎の『痴人の愛』があがっているのに、2019年では『春琴抄』へと変更されている。ちなみに、2004年の「新潮文庫の100冊」でも『痴人の愛』です。どこかの時点で、『痴人の愛』はマズイんじゃないの?という判断がくだったのだろうか。逆に、1995年や2004年にはなかった三島由紀夫の『仮面の告白』が、2019年版にはあがっている。これは何を意味しているのだろうか。まあ『潮騒』よりかは、おもしろいだろうし。
はたして、これから十年後に、今年のものから何作品が残っているだろうか。おそらく名作とよばれるものは残るだろうけれど、現役作家のものは残っていないだろう。20年経って、その当時の現役作家の作品がほとんど残っていないところから考えるに。
(成城比丘太郎)