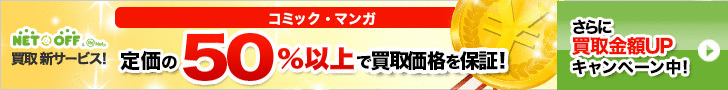円陣を組む女たち(古井由吉/中公文庫)
- 古井由吉の処女作「木曜日に」を読んでみる。
- はじめの頃から「古井由吉」は「古井由吉」だった。
- 分明と不分明をかきわけながら確かめる存在のありどころ。
- おススメ度:★★★☆☆
「木曜日に」は、古井由吉の処女作です。処女作とは、「その人が初めて作り、または発表した作品」((広辞苑 第五版 Ama))ということで、古井の場合は、大学教員(助教授)をしていた時期に論文発表や翻訳をしていたので、小説としての処女作がこれにあたります。手元にある最新の著者年譜(『聖耳』講談社文芸文庫2013年(Ama)
)によると、1968年(昭和43年)に「木曜日に」が発表されました。
『円陣を組む女たち』は短編集で、ここに収録された「木曜日に」は冒頭40ページほどの分量です。当文庫や、『行隠れ』(集英社文庫(Ama/古書のため参考))の解説では、文庫化にあたり作品にかなりの著者改訂(削除)がなされているようです。「木曜日に」がどうなっているのか分かりませんが、初期の古井が、翻訳を含めて自作に改訂を少なからずほどこしていることを考えると、本当の処女作とは雑誌掲載時のものを見なければならないのでしょう。もちろん、そこまで厳密に見なくてもいのですが、「木曜日に」は、単行本化と文庫化にあたり、著者の目を二度通った作品だということを一応しるしておきます。
では、まず冒頭をみてみます。
「鈍色にけぶる西の中空から、ひとすじの山稜が遠い入り江のように浮かび上がり、御越山の頂を雷が越しきったと山麓の人々が眺め合う時、まだ雨雲の濃くわだかまる山ぶところの奥深く、幾重もの山ひだに包まれて眠るあの渓間でも、夕立ち上がりはそれと知られた。」
はじめは、ひとつの映像の流れを、時間推移からくる様子の変化として描きだしながら、その視点が「山麓の人々」へと焦点化されていきます。または、その人々が眺めていた光景、いわば人々の(天候への)期待を集めた先にある、そういう着地点を包摂した全体として捉えられなくもありません。要は、人々の視点を入れこんだ風景(情景)描写ということです。
その次に、「山ぶところの奥深く」にある「渓間」に視点は移っていきます。その場所でも、真空の人物を仮定するとするなら、「夕立ち上がり」を知ることができるということを示しています。
この場面は、普通に読むと、視点の主体である人物は出てこないという、非人称的な視点ですすめられています。
では、その次です。
「まだ暗さはほとんど変りがなかったが、いままで流れの上にのしかかっていた雨雲が険しい岩壁にそってほの明るく動き出し、岩肌に荒々しく根づいた瘠木に裾を絡みとられて、真綿のような優しいものをところどころに残しながら、ゆっくりゆっくり引きずり上げられてゆく。そして雨音が静まり、渓川は息を吹きかえしたように賑わいはじめる。」
ここの描写にもまた、動きがあります。「暗さ」がありながらも、雨雲が「ほの明るく動き」だすのです。この「暗さ」は辺りの様子の全体でしょうが、部分に目をやると、雨雲は「ほの明る」さを帯びているのが見えるのです。ここでは、暗と明とのコントラストとともに、ひとつの明るさへの期待と何かの幕開けを、読み手に帯びさせる効果をもたらすような情景になっています。そして、雲の白い幕が上がった後に、隠されていた音があらわれて、舞台がいよいよこの「渓川」にうつることになるのです。
ここまで、この一段落を読んでみて、視点の位置変化や空間状況の変化に、明暗のうつろい、音のわきあがりが凝縮されているようで、すでにお腹一杯な感じです。
次の段落では、「宿の主人」が「午睡の重苦しさから目覚めて」、渓川にかかる「小さな吊橋」を「まだ夢心地で眺めていた」というように、ここでようやくはっきりとした見る主体が登場します。「宿の主人」が見る対象である橋は、「不気味な表情で滑り落ちる渓川」の下手にあり、読み手もまた「夢心地」にあてられたようなおぼつかなさを感じる情景です。
その(主人の)視野へ、向こう岸から「地から湧き上がったように登山服の男」が現れます。男が渡ろうとする吊橋は、(一般の)登山者が渡るときには、その者たちの「慎重な歩み」に共振するように、「うつろなきしみ声をたててうねり出す、笑いだす」ように見え、その光景を楽しむのがこの主人の楽しみです。
しかし、主人の前でこの男が渡ろうとする時には、その姿をつかませないかのように、雨霧の残る空間を揺れる橋の上で漂い出し、「何やらしきりに試し戯れるように膝で吊橋を漕いでいる」のです。
この辺りの描写は、主人という見る主体となるものがありつつも、どこか、山水画か何かに現れた光景、または、書き手が見る舞台の書割のようにも見えなくもないです。
この主人は「まどろみ」のなかをしばらく漂いながら、普段の登山者たちの光景を思い浮かべつつ、この男が来るのを待ち受け、ようやく目の前に現れた「きまり悪そうに笑う」男を中に招きいれる。
そして、主人は男に次のように言った。
「《あの時は、あんたの前だが、すこしばかりぞっとさせられたよ》と、主人は後になって私に語ったものである。」
ここで、ようやくここまでの描写がどのようなものだったのか分かるようになっています。主人に見られていたこの「男」がこの一編の書き手(語り手)だったのです。「私(=男)」に語ったその主人の言葉から状況を再構成し、語り手(=「私」)でもある人物が、さらにその時の周辺の光景をも入れ込みながら、ひとつの回想を綴ったものともいえます。これがあたっているかどうかは措いておいて、この「男」が主人公(語り手)である「私」であることが分かってから、「私」が踏み込む不分明な世界に引きずり込まれるのです。
さらにいうと作者というもうひとつの見るものも出てくるのですが、その作者も読者とともに、つかみどころのない世界を手探りで分け入ろうとすることを、次の段落から求められるのです。
一行空いて、次のように「私」の語り(追想)は始まります。
「それは木曜日のことだった。」
「それ」とは、「私」が三日間「人の姿のない木深い尾根道をひとりでたどって来て」、そうして冒頭の谷に降って来て、「温泉宿の土間に崩れ落ちて宿の人々の手で奥に運ばれて」寝かされたという、その日のことです。
このあと、「私」は山での出来事と、都会に帰ってからのこと語る(語らせられる)のですが、いずれも判然とせず、まるで、現実に対する読み手側の不確かな認識を煽られるかのようです。われわれは、はたしてはっきりとした眼で自らの記憶を判別できているのかどうか。
また、世界認識の不確かさは、吊橋が「神経質に震える」という描写にも見えます。ここには、古井作品の初期によく見られる、不気味で輪郭の捉えにくい他者のイメージが現れているようです。分明と不分明との境を絶えず確かめながら、狂気の錯覚と不眠めいた朦朧の手前で踏みとどまって、ひとつひとつ言葉を確かめながら、絶えず変成していく意識の中に現れる世界の事物を認識していこうとする傾向が、作中の「私」にあらわれてくることになります。その様は、まるでヌーヴォーロマンを読んでいるような感覚があります。
ところで、4ページほどの分量のあいだに、「笑う」という現象が頻出します。「可笑しなほど」、「笑いだす」、「照れ笑い」、「甘ったるい微笑」、「きまり悪そうに笑う」、「曖昧な笑み」、「すまなそうに笑いかけ」、などと人物だけではなく、モノまでもが笑うのです。人や事物がおのれの存在をもてあますとき、顔が破れるように、自身に秘めていたそれが崩れだしてしまうのです。ものに憑かれたような放心と、それに気付いて、何かやましいことをしていたかとふりかえるも、反省のつかみどころを逃したとき、人は羞恥につながる顔の崩れを張りつかせるのです。
古井由吉は、(作家として)比較的初期のエッセイで次のように述べています。
「小説を書くということは、つまり現実の生について虚構をめぐらすということは、それ自体すでに恥知らずをおかすことであり、現実(レアリティ)を失うことであり、それゆえ、恥ということ、現実ということについて物を思わされることになる」
(「言葉の呪術」『新鋭作家叢書古井由吉集』河出書房新社(Ama))
もしかすると、これが処女作であった古井にとって、作品を世に出す行為というのは、何らかの気恥かしさに通じるものがあったのかもしれません。「虚構をめぐらす」ということは、現実をもたらさない言葉の氾濫にその身をひたし、あるいはそれに逆らい、現実には見えない新たな現実をうみだすことであれば、その見せかけの現実をうみだしてしまう「言葉の呪術」に捉われないことが重要だったのではないか。そのときには、「書くということがすでに虚構」という意識を念頭にもたざるをえず、そうして書かれたものが(改めて)現実ではないこととして立ち現れるとき、胸のうちにふくらんだ現実/虚構の行き交いは「恥知らず」の観念をうえつけるのではないか。現実に反することを平然と行う、その不遜な行為についての観念を。このことに意識的・自覚的でない創作者は、いかに有り得ない現実を生み出そうとも、「言葉の呪術」に使嗾されただけの、文字通りにただの「恥知らず」なのかもしれません。
言葉には、「聞き手読み手の人格を通り越して情念の深層に直接働きかける」呪術的ともいうべき効果があると古井はいいます。もしかすると、「言葉の過剰さ」は、虚構をつくりあげるだけでなく、それと現実との両義性をうみだすのかもしれません。その両義性に両足をすくわれそうになりながら創作をしていくことが、ひとつの書き手の倫理のようにも思えます。
過剰になった言葉は、虚構の枠を取り払って、人間の拠って立つ現実を揺り動かす呪術的な力を持つのですから、その過剰さにさらされた人間は、不可避的に小説(文章)を読むという現場に向き合わされるのです。私が、古井由吉作品を読む時に感じるのには、こういうこともあります。
古井は、「言葉の呪術のもっとも単純で強い表われは擬声語」と「常套句」ということを述べており、また、「文学のおぞましい属性のひとつである煽情的な性格」に、創作者となって気付いたということのようです。日常的に用いられる言葉がいかに呪力を持つのかは、実際に作品を朗読したら分かるかもしれません。また、あまり関係ないかもしれませんが、だからこそ、なぜ世に氾濫するヒット曲の歌詞が定型的なのかも分かったような気もしました(ほんまかいな)。
【最後に、愚痴のようなものを】
ここまで「木曜日に」という短編小説の5ページほどを読んだだけです。この後もひとつひとつ読むことはできますが、そうするとかなりの文章量になりそうなのでここで一旦終わります。まあ、筆者である私の要領が悪いだけなんですが、それだけこの文庫作品は内容密度が濃いというか、じっくり味わいたい作品なのです。だからこそ、どこかで文庫化か何か復刊してくれないものか。最近出版された「自撰作品集」シリーズにも収録されてないみたいだし(著者がいやなのかなぁ)。この文庫に収められてるのは、他にもいい作品だらけなんだがなぁ。『自選短篇集-木犀の日』に収められた「先導獣の話」だけしか(新品では)読めないとは。
(成城比丘太郎)