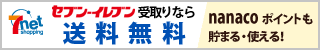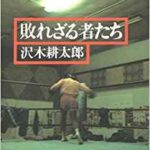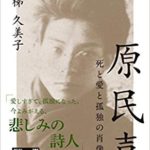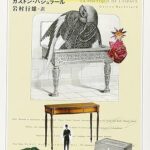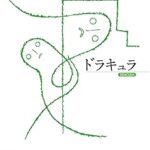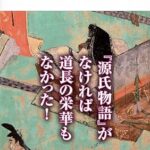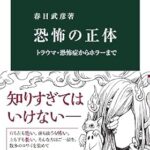誰もが知っている「貞子」の原点
呪いのビデオテープで呪いが伝染する恐怖
ホラーの古典としておススメ
おススメ度:★★★★☆
1990年以降のホラー小説としては、最も有名といっても過言ではない「リング」。現在では「リング」のタイトルそのものよりも「貞子」がキャラクターとして定着している。最近でも「貞子 vs 伽椰子」といった映画が公開されたりして、もはや「怖いキャラ」というより「マスコット」だ。今回は一応リアルタイムで原作を読んだ者として、もはやホラー小説の「古典」になっている本作が、何が当時に斬新だったかを説明してみたい。
ストーリーは大体ご存知だと思うが、完全にネタバレ状態で、核心にも触れて要約するとこんな感じだ。
同日、同時刻に恐怖の表情を残して死んだ4人の少年少女。雑誌記者で主人公の浅川は、その事件に不信を抱き、友人の高山と一緒にその原因は「呪いのビデオ(テープ)」にあることを知り、そのビデオの作成者として、超能力者の「山村貞子」の名前を探り出す。二人は貞子の過去を調べ、貞子が呪いを込めてビデオを念写したことを知る。貞子の遺体を供養することで、その呪いを解除しようと思うが、供養しても高山は結局呪いで死ぬ。主人公もテープを見ていたが死ななかった。その差が「ビデオテープのダビング」つまり「人に観させる」ことにあると気づく。家族もビデオを観ていたので、誰かにテープを見せて助けようとして終わる。「呪い」は拡散していくのだ。
私が考えるに3つのポイントが斬新だった。
一つ目は「ビデオテープ」という「家電」をメインに使った点だ。今や現実に見ることもほとんどなくなったビデオテープだが、初版の1991年では3億台以上も普及していた現役の「必須家電」だった。ゲームをやる人ならわかると思うが、初代ファミコンが全世界合わせても1億台余り、3DSで現在8000万台だ。その「家電」というものと「呪い」という組み合わせの妙が素晴らしかった。「まさかこんなもので」という衝撃があった。
次に「観たら呪いが伝染」というわかり易く、かつ、身近な方法だったことが怖かった。誰の家にもあるビデオテープ。「ひょっとしたら、今観ているビデオも呪いのビデオテープでは」という、実感を伴った恐怖を抱かせた点が秀逸だ。映画やドラマなら「このリングという映像を観た私たちもヤバいかも」と思うだろう。
3点目は「緻密なルールと細部」だ。再読してみたが、構成が優れていて、れっきとしたホラー小説でありながら、ミステリやサスペンスの要素が巧みに盛り込まれている。特に、ビデオを観てから「7日間で死ぬ」という時限性の爆弾のような設定が効果的だ。「恐怖を味わう十分な時間」と「助かる方法を推理する」ということが、作品に緊迫感を与えている。さらに実在の人物「高橋貞子」をモデルにしているのも説得力がある。「もしかしたら、マジ話かも」というリアリティが加わった。
当時、ホラー小説と言うのは、今と比べれば軽く見られていたジャンルだった。それを「大人が真面目に読む作品」として世間に認識させたのは、鈴木光司氏の功績だ。さすがに、今の中高生にビデオテープを説明するのは難しい(DVDやBDはダビングすると違法)ので、手放しではおススメしないが、モダンホラーの古典として読んでみてはどうだろう。
ちなみに、現在定着している貞子の風貌は原作では相違があり、あの「貞子の姿」を生み出したのは、映像化した人間のデザインだ。今やコメディエンヌかと思うほどの「貞子」だが、そういう違いを探してみるのも面白いと思う。
(きうら)
 リング(楽天) |