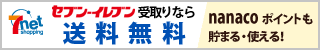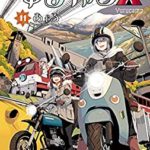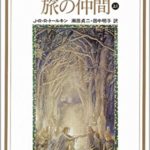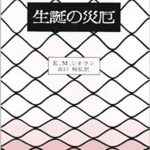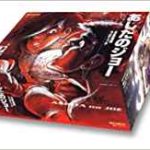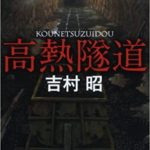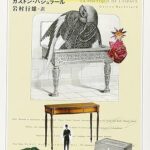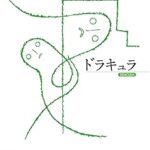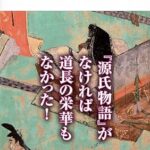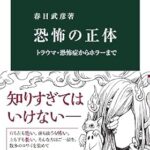2編とも短くて簡単に読める。
桜には魔力のようなものがある(個人差あり)。
狂気と正気のあやうい均衡が感じられる。
おススメ度:★★★★★
「桜の森の満開の下」は、桜の魔力にあてられた山賊と、彼が奪い取った女をめぐる幻想的な物語です。女は山賊のもとにいた彼の妻たちを一人残して全て殺せと命じます。なんとも恐ろしいです。特に凄惨なのは、二人と「女中」との三人が都に上り、そこで日夜行うある遊びです。このシーンを映像化するとなかなかグロい感じですが、話全体(ラスト含めて)に漂う雰囲気が哀しげなせいか、あまり気持ち悪くは感じません。
安吾は、桜の下でのドンチャン騒ぎは江戸時代以降のもので、それ以前の人々は桜の下はおそろしくて、足早に素通りしていたと書いてます。西行も花(桜)の歌を多くよんでますが、現代人とは桜の捉え方が違っていたのでしょうか。まあ確かに人影のない桜並木に突然迷い込んだら(入る、より怖い)、その空間が異質になったように感じます。桜が多ければ多いほど圧倒されます。3月まで葉が落ちていて裸木だったのに突然薄ピンクの森になるわけだから、心が騒ぐのも何となくわかります。今はソメイヨシノが全盛なので昔とは見る光景が違うでしょうが。
「桜の樹の下には」の冒頭部分は、小説や漫画など様々なメディアで取り上げられています。久々に再読したら、〈桜の樹の下には屍体が埋まっている!〉と〈!〉マークがついているのに気が付きました。とてつもない発見をしたということなんでしょうか。〈俺〉は桜の美しさに何故不安を覚えるのか、その原因に気付いたのです。実は桜の樹の下には無数の屍体が埋まっているんじゃないか、だから美しいんだろう、と夢想した時に驚きを伴った天啓のようなものが下ったのです。
作品の最後で〈俺〉の狂気すれすれの空想が浮かんできてはじめて〈俺の心象が明確〉になる。〈今こそ俺〉はさっぱりした気持ちで〈花見の酒が呑める〉というが、この考えはかなりおそろしいのではないでしょうか。梶井の「闇の絵巻」からイメージして例えると、”谷間の闇に浮かぶ白く輝く道を、その周りが深淵と知らず、うかれて歩くようなもの”、ではないでしょうか。よく分からないかもしれませんが。人はそんな妄想にとりつかれて旨い酒が呑めるか、どうか。私(筆者のこと)は多分呑めます。
これらを読んで花見に行くとおもしろいかもしれません、おそらく。
編者注)桜の下の話はよく聞くが、こうはっきり意識したことがな
かったので、新鮮だ。梶井基次郎は「檸檬」くらいしか分からない門外漢である(笑)
 (楽天) |