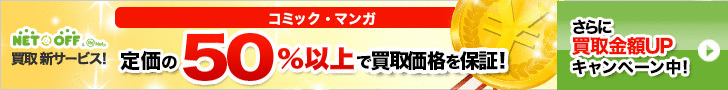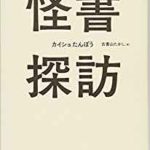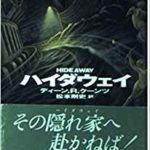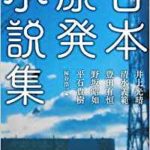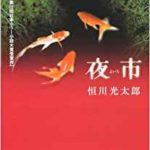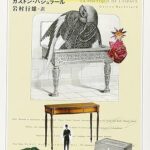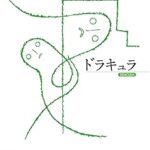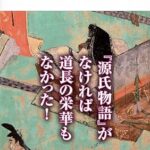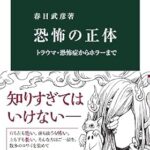- ドラクエの進化と限界
- キャラクターは悪くない
- 抽象化という偉大さ
- おススメ度:★★★☆☆
PlayStation5を買ったものの、一向に「次世代ゲーム」が登場する気配がナイ。テクノロジーの進化に対して、ゲーム自体のの進化が追いついてない。Nintendo SwitchはPlayStation5より遥かに低性能だが、ソフトウェアの工夫で市場を支配している。古い時代は性能が足らない為に表現できないアイデアもあった。しかし今、コンシューマー向けゲームが突き付けられている現実は、アイデアを実現するための資金がないという状態だ。高性能化によってグラフィックスは美しくなった。同時にそのグラフィックスの構築に手間がかかり、開発費用が暴騰した。並行して、スマホゲームというコンシューマーゲームと似て非なるものが席捲するようになり、居場所を奪われた。まるでCG革命を終えて衰退の一途を辿るハリウッド映画のようではないか。
私は今日まで変わらずゲームとは「未来との対話」であると思っている。今なお、心震わされるテクノロジーとアイデアの融合を夢見ている。それはこれまでに幾度も感じたゲーム特有の素晴らしさだろう。スマホゲームを全否定はしないが、そこに射幸心やソーシャルのリアルの勝ち負けを持ち込んだものは、何かしらの冒涜のように感じる。私はゲームの制作者たちと対話はしたいが、その消費者とは別に関わりを持ちたくない。また、いつまでも完成されない課金を必要とする世界は、自我の肥大や他人との競走、単なるコレクションという贅肉をゲームに持ち込んだ。閉じた世界の果てにある精神的な秘境へ飛び込むのがゲームである。今ムカついた人もいるだろう。なので、これは私の宗教かも知れない。
そんな私にとって、永らくバイブルであったのが家庭用ゲームのドラゴンクエストだ。初代をリアルタイムで遊んだ時の感じだ不思議さは今なお生々しい。「こんなものがあるのか?」という異質さ。そしてそれはドラゴンクエスト5で、パーフェクトに完成され、ゲームだけの感動であることに気付く。ところがそこからは自己模倣に反転し、形は少しずつ変えつつも再びゲームの頂点に君臨することは出来ていない。先にオフライン版が発表られたMMO RPGのXは除いての話になるが、ドラゴンクエスト6以降は、その時代の一周遅れの技術を用いて、同じような感覚のストーリーが展開されることになる。いや、ドラクエは技術的にはいつも同世代のゲームより劣っていたのだ。ただ、そのゲームの作劇方法で他を圧倒していた。そしてドラゴンクエスト11、発売は2017年で既に4年近く経過し、次回作のドラゴンクエスト12も発表されている。
私はこのゲームが発売された当時から、すでに時代遅れなゲームであると感じていた。その為、敢えて遊ばなかったのだが、ここで冒頭に戻る。PlayStation5で遊ぶゲームが無くなったのである。そこで、封印を解いて、ついに購入した。「かつて好きだった人の老いた姿を見るような怖さ」という事前の感想は半分当たっていた。ただ、かつての絶対王者の片鱗も見えたというのが正直な感想だ。
今作では主人公は勇者でありながら、悪魔の子として追われるストーリーが展開する。これまでの作品へのカウンター的なストーリーだ。この点は悪くない。オチ、大オチが贅沢に用意されている。前時代的過ぎて少々辟易する演出場面も多すぎるが、物語の大筋は楽しめる。
しかし立体化された世界で、これまでのドラゴンクエストの世界観を再現するのは無理があった。同じく3Dのドラクエ8でもその感慨はあったが、グラフィックスの進化によって色々な不都合が顕著になっている。
例えば同じスケールのキャラクターが町や村もフィールドも迷宮も歩くことにより、相対的に広いはずのフィールドが狭くなり、狭いはずの村が広くなってしまった。これはもうどうしようも無い違和感がある。船に乗ると一応プレイヤーは船の画像になるが、世界そのものもずいぶん縮んでいる。一番狭いのが世界全体で、次にフィールド、迷宮、大きな町という不可解な逆転が起きてしまった。これでは冒険してる感がどうしても薄れてしまう。かと言って、町を小さくするとリアリティが無くなってしまう。さらにドラクエは伝統的に隅々まで探索するゲームだ。それだけに広い町を見るとそれだけで面倒くさい。これは2D時代から言われていたが、小さなメダルを集める為に他人の家に侵入して瓶を割るという行為も、中途半端にリアルなのでもはやギャグのようだ。ただ、入れる家はかなり制限されているので、調整はしているようだが。
CGで人物を描くと、本物の人間にもイラストにも見えず、いわゆる「不気味の谷」と呼ばれるリアルと非リアルの間に陥ってしまうことが未だに多い。本作の主人公たちは鳥山明の絵を再現したアニメ調なので、それは回避しているが、システムがリアルと非リアルの間に陥ってしまい、結果的にゲーム全体が不気味の谷に陥っているような不自然さが目立つ。
ドット絵時代のドラクエが優れていたのは、明らかにアイコンにしか見えない勇者たちに、息を吹き込むテキスト、それを彩る音楽と敵キャラのデザインがあった。ドラクエ11の主人公達はリアルになったし、ボイスまであるので、キャラクターとしては面白い。反面、想像力を必要としないので、とにかく制作者が意図した演出しか見えない。それはとんでも無く長いムービーシーンの多用に現れていると思う。もはやライバルだったFFをムービーゲーと笑えないレベルだ(今は同じ会社だけど)。とにかく何でも律儀に省略しないので、話に乗ってる時は面白いが、どうでもいいサブクエストはうんざりする。制作者もそこは分かっていて、とにかく短く、面倒臭くないようにしようという努力は見える。走る速度はかなりのもので、その気になればほとんどの敵を避けて突破できる。戦闘シーンでの特別な技の発動ムービーは飛ばせる。極め付けはわざわざ全編をドット絵で遊べる2Dモードの搭載だ。
本編でも過去作の名シーンの裏側をドット絵で楽しめる「ヨッチ村」というものがあるが、結果的にドット絵は失敗だ。やってみると分かるが、ドラクエ4以上5未満といったグラフィックスで、こんなことに労力を使うなら本編のシステムを改良した方がマシだった。ドット絵は現在はほとんどロストテクノロジーになっている。全盛期は8色や16色である種芸術的な絵が表現されていたが、ドラクエ11の2Dモードは単なるダウンサイジング、あるいは劣化コピーされただけで、制作者の熱意を感じない。しかしまあ、それを承知で全部作ってしまうのは凄いとも思う。他の企業には真似の出来ない物量作戦だ。
ちなみに3D表現は進歩したといっても、元がSwitch準拠なので、イベントシーンはムービーになったりして、フルリアルタイムレンダリングでは無い。いくら王国と言われても50人も住んで無いような広さに思えるので、これもリアル化が災いしていると言えるだろう。
ゼルダの伝説のブレスオブザワイルド、ゴーストオブツシマなどは、この辺をうまく処理していた。逆説的になるが2Dモードにできるものを3D化するのは無理があるのだ。やはりどこかでプレイヤーの想像力を働かせる仕掛けが欲しかった。
文句ばかり書いたが、仲間のキャラクターの個性については「良いステレオタイプ」で愛着が湧いた。最後まで進めたのはこのキャラの魅力によるところが大きい。しかし、今の時代、シルビアのようなキャラには問題は無いのだろうか? この辺、日本でもどうかと思うくらいなので、海外で叩かれないか余計な心配をした。
まとめ:これまでのドラクエで好評だったことは全部盛り込んだ。敵のキャラの使い回しは気になるが、物量もかなりのもの。しかし、これはやはり2Dゲームの3D表現であって、そこにゲーム的革新はない。結果、肥大した物量ばかりが目立つ、仲間との会話を楽しむサウンドノベル的なRPGになってしまったように思う。それはそれでありだが、ドラクエに期待するものとは違う。それも分かっていての副題「失われた時を求めて」なら、納得する。制作者も限界を自覚していたのだろう。
エヴァンゲリオンと同じく、さよならでもなく、また会おうでもなく、お疲れ様、と言いたい作品だった。
(きうら)