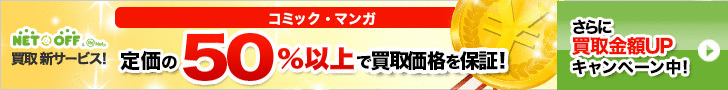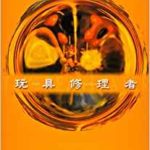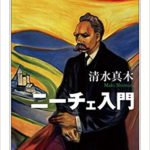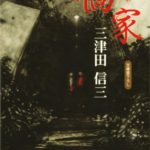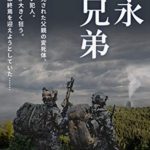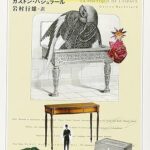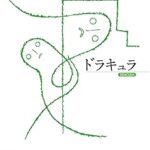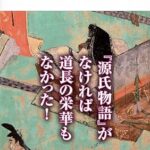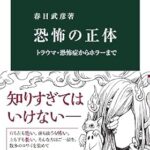- 読書メモ(026)
- 日本文学にみる古代から近世までの「幽霊」観念
- 幽霊は死者というものの記憶装置
- おススメ度:★★★☆☆
本書は、日本において「幽霊」という観念がどのように生まれたのか、またそれがどのように変遷したのかを、主に文芸作品からみていくものになっています。「幽霊」とは、字義通りに解釈すると、死者の霊(人間の霊)となるわけですが、それは人間が死ぬとどうなるのか死後どこへ行くのか、という「他界観」と深く結びつくものになっています。とくに、「他界観」に関しては中国(文学)からの影響ぬきには考えられないのがわかります。
【注】本書は、30年前に出版されたものなので、内容的に古いものがあるかもしれません。そのなかでは、フェミニストが読んだら卒倒しそうな見解もありますが、そこらへんを無視するとそれなりに面白く読めると思います。
まずは、幽霊と妖怪とは何が違うかについて述べられます。両者は区別できるのかそうでないのかは、人によって意見の分かれるところです。幽霊は死んだ人間だけであるとか、妖怪は生きているモノだけであるとか、幽霊は場所に憑くだけであるとか、幽霊は他界と関係があり妖怪は異界の存在であるとか。このふたつの概念規定は截然と分かれるかどうか現在どうなているのか分かりません。また考えることにしよう。
日本(文学)においてはじめて幽霊が現れるのは、平安時代のはじめですが、それは明らかに中国文学の翻案でした。それから日本独自の幽霊像が現れるのは『今昔物語集』だそう。そこには日本人の幽霊観と他界観との関連がみえるといいます。古来よりあると思われる祖霊信仰があったとしたら、そこから生者に対する死者側の好意があったという信念がうまれたのかもしれません(一方、アニミズム的なものは妖怪化の源泉になったかもしれません)。それゆえ、平安中期までの幽霊には、現在見るような怨霊化した霊は出てこないようです。
仏教渡来以来、「カミ」や「霊魂」といった観念が、仏像仏画同様何らかの形で人間の姿を模して表象されたとするなら、仏教はやはり(?)多大な影響を日本に与えたといえるかもしれません。それから火葬の導入もまた、<肉体のない霊魂だけの存在>といったようなものを、より一層生きている者に強く意識させたのかもしれません。
「幽霊」そのものは中国の影響抜きには考えられないのですが、そこには他界としての地獄観念が大きく含まれているようです。「冥土と現世を往還する鬼や幽霊」が日本の「幽霊」のモデルのひとつとするなら、中国の志怪小説からその観念を引き継いだといえるでしょう。しかし、その地獄観としては日本独自のものも生まれました。日本の地獄観というのは、簡単に言うと、えげつない所だということです。よく目にするような地獄絵や、現代まである程度継承しているヒドイ場所としての地獄像は、日本人特有(?)の暗い想念を表していて、それはやがて怨霊化する「幽霊」につながるようです。やがてその怨霊は、怨霊への畏怖を表す「御霊信仰」にいきつきます。それはつまり、「幽霊」というものを共同的な幻想として、「公的な存在」とするということです。
近世になって様々な「幽霊」の出てくる文芸作品が誕生しました。共同的な幻想として、ここではみんなで共有する「幽霊」を楽しむという余裕がでてきたのでしょうか。よく知りませんが。今でもよく耳(目)にする<現世にさまよい出る幽霊>という観念は、あきらかに「中有」観念の影響があるようですが、今でもそういった観念があるとするなら、仏教導入は本当に大きいのでしょうねぇ(二度目)。本書では、現代の「幽霊」については述べられていませんが、現代人の「他界観」が古来よりとくに変わっていなければ、それについて何かしら語ること(つまり死んだらどうなるかなどといったこと)は、「幽霊」と大きく関わりがあると思われます。そしてそこには、死者の行末(への妄想)だけでなく、生きている者が死者をどう扱うかという、死者の記憶装置としての「幽霊」観念があると思われます。たとえば、夢幻能などといったものに現代人でも何かしら感動できるものがあるとしたら、「幽霊」といった超自然存在にも十分居場所はあると思われます。「幽霊」概念がこの先変わることはあっても、「幽霊」への扱いにおける(日本人の)心性は当分変わることはないだろう(と思われます)。
(成城比丘太郎)